「心理的資本開発士 PsyCap Master」のホリシンです。
今回は「哲学的思索」と「心理的資本」の関係についてです。
「深く考える時間」が「心理的資本」を磨く。たまにはまじめな話をしよう。
若い人が本を読まなくなったというのは時代の趨勢として仕方がない面もあります。
しかし同時に「考える」ことも放棄してしまったとしたら、それは由々しきことではないでしょうか。
「検索すれば答えが手に入る」から考える必要がないという若い部下に向けて、管理職はどんなメッセージを伝えたらいいのでしょうか。
ここでは「哲学的思索」が「心理的資本」をアップデートさせ、いかに人生に大きな影響を及ぼすかという文脈で、管理職のみなさんが「考えない人(部下)」とのコミュニケーションに生かしていだだけるように構成しました。
まずは部下の方に「たまにはまじめな話をしよう」と言ってみてください。

「哲学的思索」とは何か、そして何を生むのか
「哲学的思索」という言葉を聞くと、難解な禅問答や抽象的な議論を思い浮かべるかもしれません。
しかし私が考える「哲学的思索」とは、「人生や物事を深く考え、そこから新たな気づきを得る」思考のプロセスのことです。

たとえば、「なぜ自分はこの仕事をしているのか」「20年後、どんな自分になっていたいか」と問い続けることもその一つです。
こうした「哲学的思索」は、「正解」を得ることが目的ではありません。
自分の考えを掘り下げ続けることで、迷いながらも前進し、次第に心が着地点に向かい、おぼろげながら人生の指針が見えてくるといったものです。
私自身も、キャリアアップ一辺倒だった若い頃を振り返ると、「なぜあのとき、もっと立ち止まって深く考える時間を作らなかったのか」と反省することばかりです。
その反省と後悔が、いまこのような文章を書く動機となっています。
「思索」と「思考」の違い
ここで「思索」と「思考」の違いについて考えてみましょう。
「思考」は、日々の問題解決や意思決定のために行う活動です。

仕事においては、次のプレゼンをどう成功させるか、目標をどう達成するかなど、具体的な課題に対する解答を得るためには「思考」をフル回転させる必要があります。
一方「思索」はというと、もっととりとめがなく広がりのあるものだと思います。
「この仕事を通じて、私は何を学び、どんな価値を世の中に生み出しているのか」「自分は家族にどのような影響を与えているのか」といった問いを自分自身に投げかけ、自分の立ち位置や人生の意味を深く考えることです。
私が思うに「思索」には、正解を求めるロジックと焦りは不要です。
ただ、禅問答のように問い続け、考え続けることが大切なのだと思います。
家族や人生、世界について深く考える時間の必要性
日々の仕事に追われていると、「考える暇なんてない」というのが現実でしょう。
私自身も35年間の広告業界でのキャリアを振り返ると、目の前の業務をこなすだけで精一杯だった時期がありました。
しかし結局は忙しさに流されて日々をやり過ごすだけで、気づいたら「何のために働いてきたのか」という虚しさに襲われることになりました。
「哲学的思索」を導くためのひとつのヒントは「家族」です。

自分の存在は「家族」にとってどんな意味があるのか、と問いかけることで「思索」が広がっていきます。
部下を指導する際にも「家族を大切にしなさい」と伝える管理職は多いでしょう。
しかし、自分自身が家族や人生について深く考える時間を持てていなければ、やはりその言葉は軽く響いてしまいます。
検索やゲームからは「思索」は生まれない
Z世代を部下に持つみなさんなら、彼らがスマホを片手に常に何かを検索したり、ゲームを楽しんでいる姿を目にすることが多いでしょう。
情報を得ることや娯楽を楽しむこと自体は悪いことではありません。

しかし、それだけでは「思索」は生まれません。
検索で得られるのは、瞬時に手に入る「答え」であり、人生への「問いかけ」を持つきっかけにはなり得ません。
ゲームも一時的な達成感は与えてくれますが、そこに人生の意味につながる深さはありません。
だからこそ、管理職である世代が、深い問いかけを持ち、考え続ける姿勢を示すことが大事だと感じます。
「20年後の自分」をイメージする
「20年後、どんな自分になっていたいか?」と聞かれると、多くの人は「何をしているか」を答えるかもしれません。
役職や収入、生活スタイルといった外面的な要素です。
しかし、「哲学的思索」の中で考えるべきは、「どんな人間になっていたいか」という問いです。
私自身もかつてはキャリアアップばかりを考え、次の昇進やそれにつながるプロジェクトの成功にばかりに目を向けていました。
しかしいま振り返って思うのは、「もっと心根のいい人間になっていたかった」ということです。
いまでも仕事で成功するだけでなく、家族や部下から信頼される人間力を持った存在でありたかったと思っています。
「歴史」を学び、「宇宙」を知ることで広がる思索
「哲学的思索」を深めるためには、「歴史」や「宇宙」について考えてみることもいいかもしれません。
「歴史」からは、人間がどれだけ失敗と挑戦を繰り返してきたを知ったり、様々な時代や文化の出来事から、物事を一面的に捉えず、多角的に考える力が養われるでしょう。
「宇宙」の壮大さを知ると、自分の悩みがいかに小さなものであるかを感じられます。
宇宙は未知に満ちており、その無限の可能性を前にすると自然と好奇心がかき立てられます。
こうした「歴史」や「宇宙」に対する探究心を持つことで新しい学びや挑戦に意欲的になり、自己成長につながります。
実はこれが「心理的資本をアップデートする」ためのインスピレーションを与えてくれます。
「心理的資本をアップデートする」ことで人生のウェルビーイングにつなげる
「心理的資本」とは、「Efficacy(効力感と自信)=自分ならできるという感覚)」、「Hope(希望、目標)=未来への期待」、「Optimism(現実的な楽観性)=物事を良い方向に捉える姿勢」、「Resilience=困難を乗り越える力」の4つのリソースを指します。
数多くある「心」のリソースの中でも、ポジティブな行動を起こすための「心のエンジン」と言われる、選りすぐりのリソースなのです。
この「心理的資本」を日々アップデートしてゆくことで、揺らがない「心のインフラ」が生まれ、よりよい人生を歩むための基盤が築かれます。
「哲学的思索」を通じて「心理的資本」がアップデートされると、ただ仕事の成果とキャリアアップを追い求めるだけの人生ではなく、自分らしく心豊かに生きる人生に進むことができるようになります。
それが最終的には人生のウェルビーイング(幸福と充実感)につながります。
おわりに:いくつになっても「哲学的思索」を忘れないこと
部下であるZ世代のみなさんに「深く考える時間を持とう」といきなり言っても、響かないかもしれません。
しかし、まずは管理職である世代が、思索する姿勢を示し、深い問いかけを持ち続けることが第一歩なのです。
それが「心理的資本」を磨き人生を豊かにする方法だと、私は自らの経験を通して確信しています。
そして歳をとってもこの「哲学的思索」を続けていくことです。
私の好きなロダンの言葉です。
「石に一滴一滴と食い込む水の遅い静かな力を持たなければなりません」
「20年後、私はどうありたいか?」
この問いかけが「哲学的思索」のスタートラインです。
(ホリシン)
「心理的資本」の基本はこちら↓

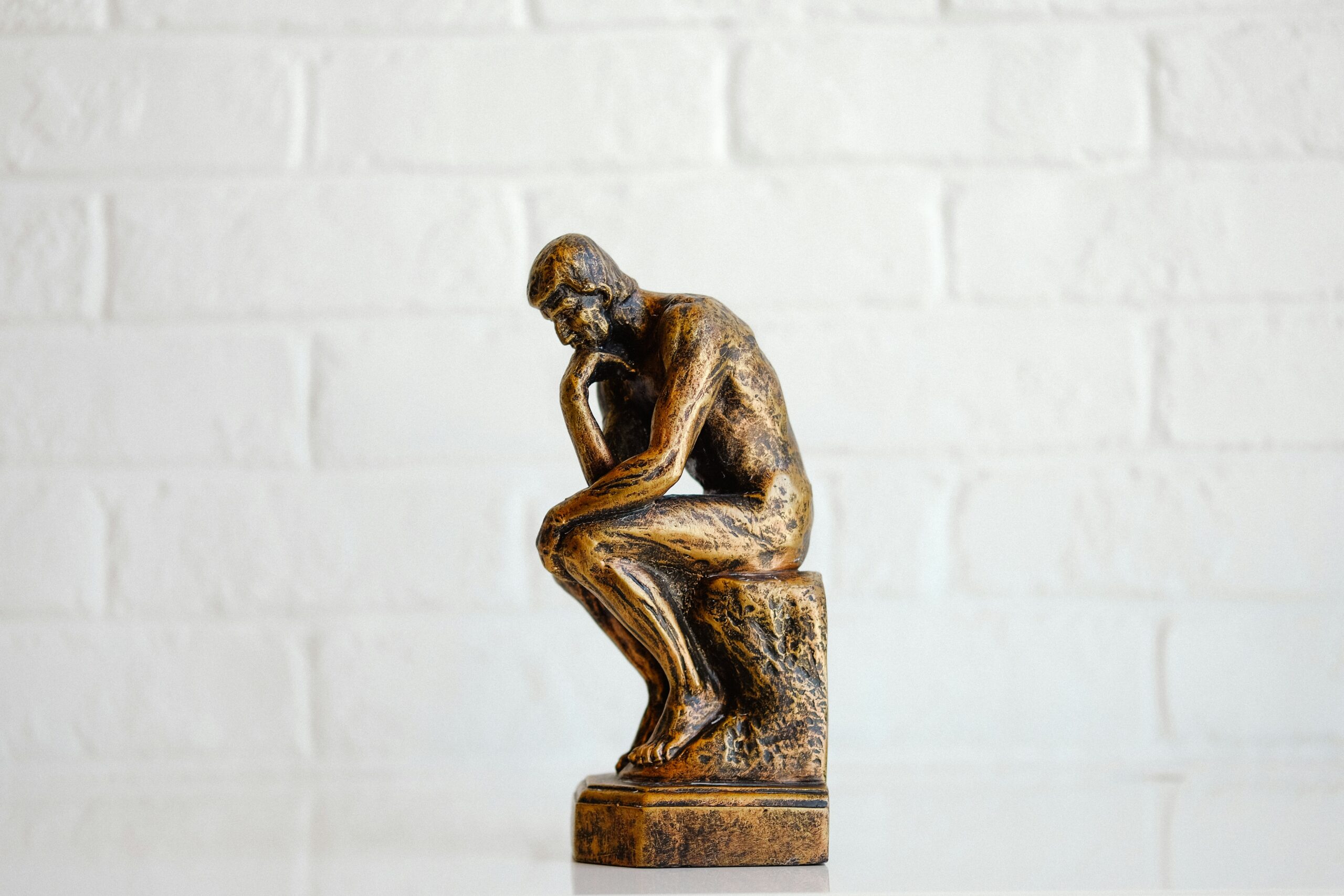


コメント